【在宅っくす。導入事例】人を育てることで、お客様の満足度向上を目指す。

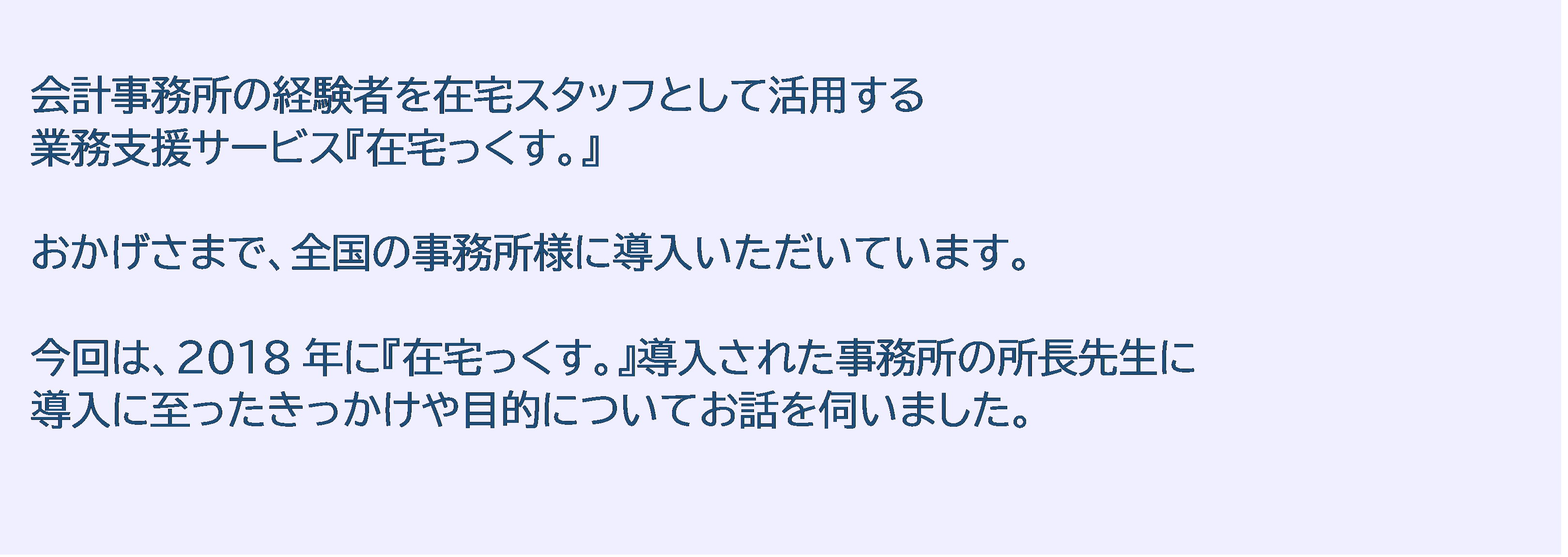
お客様の未来を見て提案できる事務所へ
―今後の展望について教えてください。
これから会計処理の自動化がどんどん進んでいくでしょう。
会計処理だけでなく、会計事務所の業務の多くが、人の手を介さずに行えるよう
標準化されていくかもしれません。
時代は恐らくそういう方向に進み、我々はそういった時代に生きていかなければなりません。
このように、人が行うアナログの作業がITなどにより電子化されていった場合、
私たち人間にしか提供できないものは何かということが非常に大事になってくると思います。
その一つが、お客様の未来を見て提案できること。
これはお客様にとって必要で、かつITには担えないところだと思います。
そのようなサービスが提供できる会計事務所にしていきたいですし、社員やパート職員にも、
そういった提案ができるようにどんどんステージアップしていってもらいたいです。
社外に人材を確保しておくことで柔軟に対応できる
そのために、入力処理や作業の部分を社員やパート職員から切り離し、
在宅スタッフに依頼できる体制をいまから作っておくことが大切です。
仮に入力が自動化される時代がきたとしても、
在宅スタッフにはまた別にお願いする業務分野が出てくると考えています。
業務をお願いできる人材が社外に確保できているということであり、
在宅スタッフの数が多ければ多いほど、
事務所としては柔軟な業務の組み立てができると考えています。
その意味で、在宅スタッフが不要になることはない、と考えています。
今まで自分で入力していたものを在宅スタッフに依頼することで、
決算処理に時間をかけられるようになったり、経営計画の作成や診療実績のデータ分析など、
お客様満足度向上につながる仕事ができつつあるパート職員も出てきています。
もちろん、個人の事情で「まだ、今のステージにいたい」と考える人もいるでしょう。
それはその人の選択を尊重しますし、時期がきたら業務ステージを上げてくれることを期待します。
私は経営者として、このように人に育って欲しいと考えています。
『在宅っくす。』の紹介はこちら
「在宅スタッフ活用」についてのセミナーはこちら

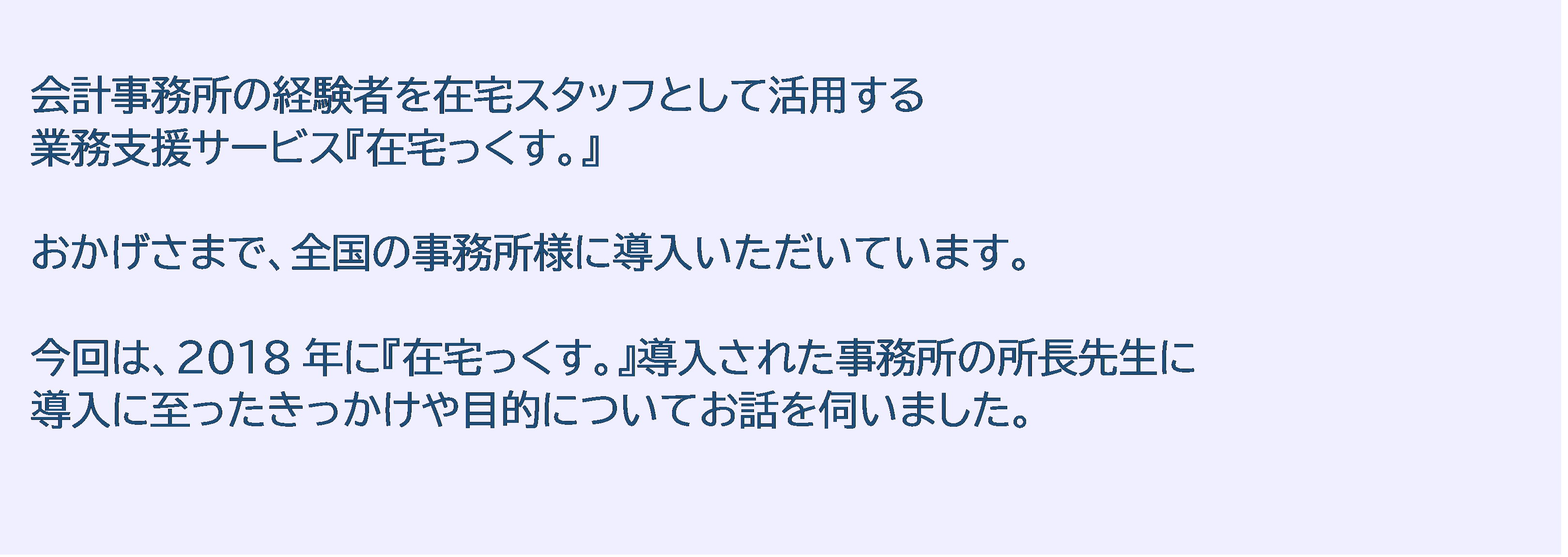
多くを伝えなくてもわかってくれる
―在宅スタッフの仕事振りについて教えてください。
最初は、どういう仕上がりで納品されてくるか全く予想できませんでした。
ところが、納品されてくると思った以上に精度が高く、
「これはいけそうだ」と手応えを感じました。
その後もやりとりを繰り返すごとに、
多くを伝えなくても分かってくださるような感覚を持てるようになってきました。
意識してコミュニケーションを取ること
―在宅スタッフとのコミュニケーションで工夫されたことはありますか。
入力を見るとスタッフさんの精神状態が分かると言うか、
モチベーションの上下を感じることができます。
そのようなときは意識してコミュニケーションを取り、業務量を調整しました。
普段からコミュニケーションを取っておくことで、こちらの繁忙期など、
「いつもより多いので断られるかな」という量をお願いするときも
受けてくれやすくなると思います。
お互いに出したい業務量、受けられる業務量を把握するために、
向こう1週間~2週間ほどの依頼予定をエクセルシートにまとめ
あらかじめお見せして相談する方法も有効でした。
『在宅っくす。』の紹介はこちら
「在宅スタッフ活用」についてのセミナーはこちら

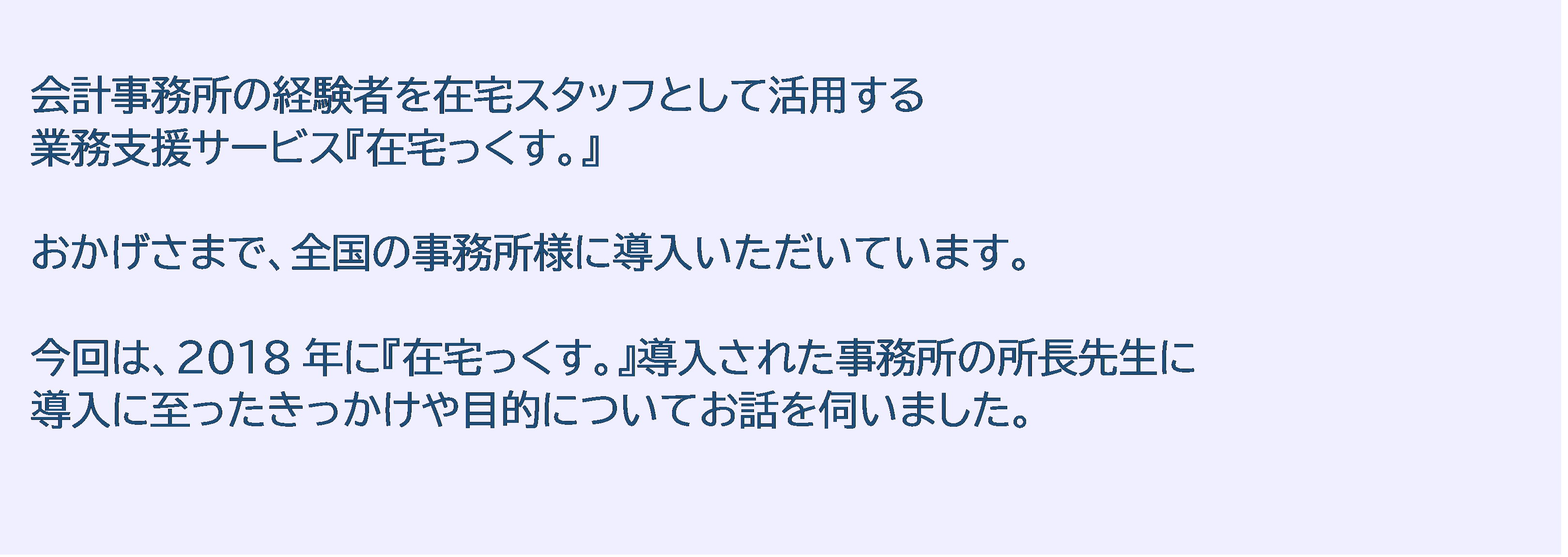
繁忙期に業務が滞らない!
―在宅スタッフ活用で、業務はどのように変わりましたか。
年末調整や確定申告などの繁忙期は、
今までは通常の月次業務と並行して作業を進めていました。
今は月次の入力作業は在宅スタッフにお願いしているので、
私は年末調整や確定申告の業務に集中できるようになりました。
年末調整や確定申告が終わると、入力が完了している状態からすぐに
次の準備をすることができるので、年末調整や確定申告といった繁忙期でも、
お客様にお待たせすることなく毎月の試算表を渡すこともできるようになりました。
「自分の時間」をコントロールできることを実感
今は、担当先の約7割の入力作業を在宅スタッフに依頼しています。
溜まった入力作業を焦ってやることがなくなったので、精神的な負担はすごく減りました。
これまでは、仕事を与えられ、それがしんどくなったときは環境を変えてもらうか、
あとは自分でとにかく早くやるという方法でしか解決できませんでした。
しかし今は、在宅スタッフと仕事をすることで「自分で道を切り拓いて、
自分で時間を削減することができた」という実感があります。
最初は大変なこともありましたが、軌道に乗せることができて自信になりました。
『在宅っくす。』の紹介はこちら
「在宅スタッフ活用」についてのセミナーはこちら

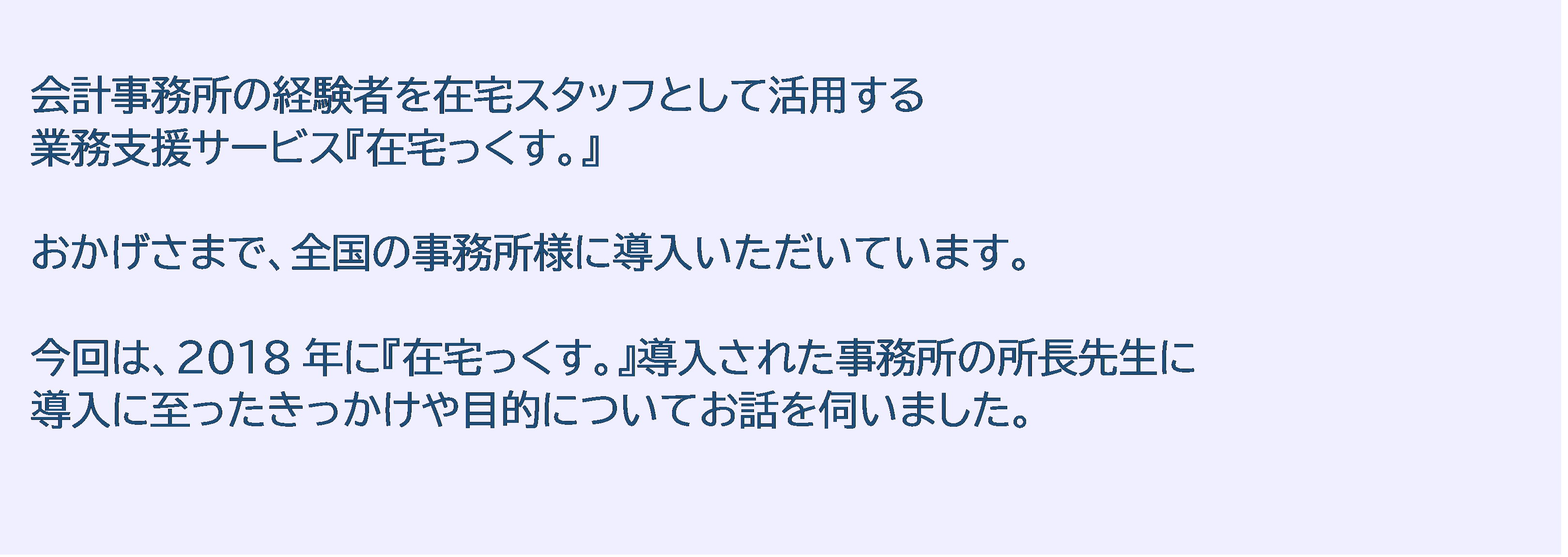
人材採用が難しい時代の、解決方法の一つ
―在宅スタッフ活用を始めようと思われたきっかけを教えてください。
人が辞めたから代わりの人を採用…と言っても、
いままでのように求人募集を出しても手応えのある応募は少ないのが実情です。
これは自分の部署の採用現場で、ひしひしと感じていました。
そんな折、エヌエムシイが「在宅スタッフ活用」セミナーを行っていると聞きました。
「これは行くべきだ」と体が動きましたね。
「在宅」というキーワードにタイムリーな何かを感じたからです。
すぐに導入すべきと思ったので、セミナーに参加し導入に至りました。
在宅スタッフには大きなポテンシャルを感じている
―『在宅っくす。』の導入後の変化を教えてください。
今回在宅スタッフ活用を始めたことで、職員も成長できたと感じています。
関わった職員は高い意識をもって取り組んでくれましたし、
どうやったらうまくいくのかを自ら考えて実行していました。
パート職員の業務ステージを上げたいという社長の思いに応えてくれています。
社員が育ってきたことにより、新しいお客様の担当を社員に分散できるようになりました。
これまでは私が新規開拓し、そのお客様を担当する役割でしたが、それには限界があります。
在宅スタッフに担当してもらえる業務範囲にも大きなポテンシャルを感じているので、
社員、パート職員、在宅スタッフを含めた発展的な組織構成が、今後可能になると思います。
『在宅っくす。』の紹介はこちら
「在宅スタッフ活用」についてのセミナーはこちら

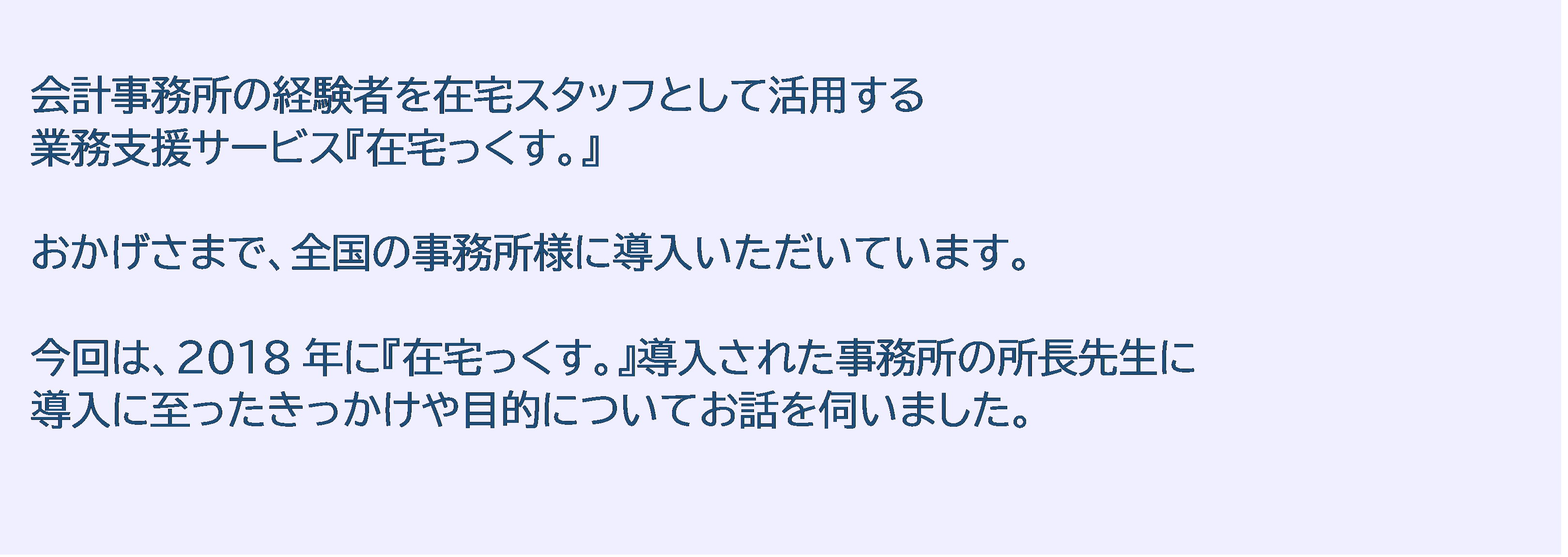
AIに取って代わられることのないスキルを
―まず初めに、在宅スタッフ活用を始めた理由を教えてください。
パート職員の教育・育成に力を入れたいと考えたためです。
私たちの事務所のパート職員は、会計入力や月次処理といった業務をメインに行っています。
しかしこれからは会計業務がAIに取って代わられ、無くなっていくと言われる時代です。
ですから社員はもちろん、パート職員にも、
AIに取って代わられることのないスキルを身に着けてほしいと考えています。
これまで時間をかけていた入力処理を在宅スタッフにお願いする体制を作ることで、
そのチャレンジを後押ししたいと考えたのが、在宅スタッフ活用を始めたきっかけです。
職員のチャレンジを後押ししたい
AIに取って代わられないスキルとは何かと言えば、色々な議論があると思います。
それを私は、「できるだけ今までやったことのない仕事」にチャレンジすることで
見つけてほしいと考えています。
彼女たちは家庭を持ち、子育てをするなどそれぞれの事情があります。
例えば子育てから手が離れ、また仕事というステージに戻りたいと思っても、
月次処理や入力処理など単純作業しかできなければ、戻る場所は残されているのでしょうか。
スキルを養うための業務は、事務所にたくさんあります。
社員はもちろんですが、パート職員にもぜひチャレンジして欲しいです。
うまくいくための仕組みが揃っている
CASH RADAR PBシステム
―エヌエムシイの『在宅っくす。』を選ばれた理由を教えてください。
じつは以前、在宅業務にチャレンジしたことがあるのです。
退職する際「在宅でなら仕事ができます」と言う社員がいたので始めたものの、
結果としてはうまくいきませんでした。
仕組みがないためにリスクやコストがかかってしまい、続かなかったのです。
エヌエムシイのCASH RADARは、データ化した資料の受け渡しや、
業務の受発注、検収チェックまでがシステム化されています。
当時うまくいかなかった問題を解消する仕組みが揃っています。
これなら進められるなと感じました。
『在宅っくす。』の紹介はこちら
「在宅スタッフ活用」についてのセミナーはこちら
大森明郎税理士事務所
所長・税理士 大森明郎 様
【INDEX】
0:00:14 事務所の沿革について
0:00:32 『私書箱』導入の決め手
【関連動画】
こういう職員に任せたら『私書箱』活用が上手くいきました
所長の『私書箱』効果。見えなかった職員の○○が見える化!
「私書箱」についてはこちら
「情報共有化」セミナーはこちら
【サービスのお問い合わせ】こちら
大森明郎税理士事務所
所長・税理士 大森明郎 様
【INDEX】
0:00:14 『私書箱』活用事務所での進め方
0:00:24 『私書箱』活用の効果
【関連動画】
もう引き継ぎ書は不要!担当替えを円滑化する方法
所長の『私書箱』効果。見えなかった職員の○○が見える化!
「私書箱」についてはこちら
「情報共有化」セミナーはこちら
【サービスのお問い合わせ】こちら
大森明郎税理士事務所
所長・税理士 大森明郎 様
【INDEX】
0:00:14 所長先生はどのように『私書箱』をチェックしていますか
0:00:24 『私書箱』活用の効果
0:01:09 今後の展望
【関連動画】
もう引き継ぎ書は不要!担当替えを円滑化する方法
こういう職員に任せたら『私書箱』活用が上手くいきました
